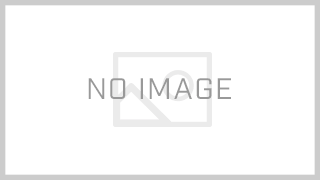企業間のコンペで勝てない、クライアントに企画を受け入れてもらえない、社内企画も採用されたことがないなど、いつも企画が通らないが、何がいけないかわからず悩んでいる方はいませんか。
企画そのもののクオリティが低いケースももちろんありますが、中には、アイデアは良いのに企画書の書き方が残念で採用に至らないケースもあります。
そこで今回は、採用される企画書を書くためのポイントをご紹介します。

企画の必要性
「いいことを思いついた!」と、やりたいことや良さそうなこと、ひらめきをいきなりアピールしていませんか。
学生時代のお楽しみ会や学芸会、文化祭の出し物を決めるようなイメージで、いきなり企画をアピールする方が少なくありません。
文化祭の出し物を決めるならそれでも良いですが、今の立ち位置はビジネスの場です。
企画を行ううえでは資金が必要となり、多くの人員が携わるなど人件費も発生します。
資金を投資しても行うだけの必要性がある企画でないと受け入れられません。
そのため、なぜその企画が必要になるのか、まずは現状の課題や問題、提案背景などを挙げましょう。
「今、こんな問題があります。」、「こんなニーズがあります。」、「良い商品なのに売上が上がっていない事実があります。」など、それは困った、それはどうにかしなくてはと思わせることが必要です。
企画の必要性を感じてもらうために、まずは問題提起を行いましょう。
企画の根拠
問題提起にあたっては、現状分析などを具体的に行うことも大切です。
世間がこう言っているから、そんな感じがするなどといった漠然としたものでは説得力がありません。
自社の商品の売上が伸び悩んでいるのも、なぜそうなっているのかを分析することが必要です。
ターゲット層に響いていない、ターゲット層はこうした問題を抱えているなど、調査や分析を行った結果も入れましょう。
具体的な施策
そのためにどのような企画を行うのか、具体的な施策を書きます。
たとえば、商品の売上を伸ばすための企画として、ターゲット層へのプロモーションを強化するだけではこれまでもやってきたことです。
これまではテレビCMだったけれど、SNSを使うでも、まだまだ具体的ではありません。
SNSを使って、どのようにプロモーションを行うのか、具体的な施策をわかりやすく提案することが大切です。
実際にその方法がわかるようイラストや図、画像などを使って説明しましょう。
企画の成果やメリット
企画を行うには資金や人員が必要になります。
そのため、行うからには結果を出さないといけません。
企画を採用してもらうためには、企画を行った際にどのような成果が出るのか、どのようなメリットがあるのかも具体的にしなくてはなりません。
どんな成果やメリットが出るのか、伝わりやすいよう箇条書きでまとめるなどしましょう。
長々と文章を書くより、箇条書きで短文で示すことで印象に残りやすくなります。
箇条書きで並べたうえで、個々の成果やメリットについて詳しく説明したほうがインパクトを残しやすいです。
視覚的なわかりやすさ
採用されない企画書は、見た目が面白くないものが多いです。
見た瞬間、読む気を失うような、読みたいと思えない見た目のものが多くなっています。
たとえば、小さな字がビッシリ詰め込まれた論文のようなものである場合や白黒で文字だけが並んでいるようなパターンです。
ビジネスの場なので、真面目に書くことが必要、たくさん書けば企画の内容が伝わると思っている方がいますが、そうではありません。
初めてその企画に接する人が、すぐに理解できるようにすることが大切です。
忙しい中で多くの企画書に目を通す場合や他企業や他者の企画と比較検討するケースも多いので、読みたくなる見た目、読んでスッと頭に入ることやイメージできることも必要です。
そのため、企画書のレイアウトにも気を付け、文字のサイズも大き目にするなどして、文章ばかりの企画書にすることは避けましょう。
現状分析の根拠がわかりやすいようにグラフや表で示すことや企画の具体的施策や成果がわかりやすいようにイラストや画像を入れるなどをすることが大切です。
不採用になった企画書の内容でも、見た目を変えただけで、読んでもらえる企画書になることや採用される企画書になることもあります。
採用される企画書を書くには、内容の具体性と説得力、見た目も大切です。
まとめ
採用される企画書を書くポイントは、企画の必要性、企画の根拠、企画の成果やメリット、具体的な施策を明確にすることです。
視覚的なわかりやすさも重要となるため、レイアウトや文字のサイズに気を付け、グラフや表、画像を入れるなどしましょう。