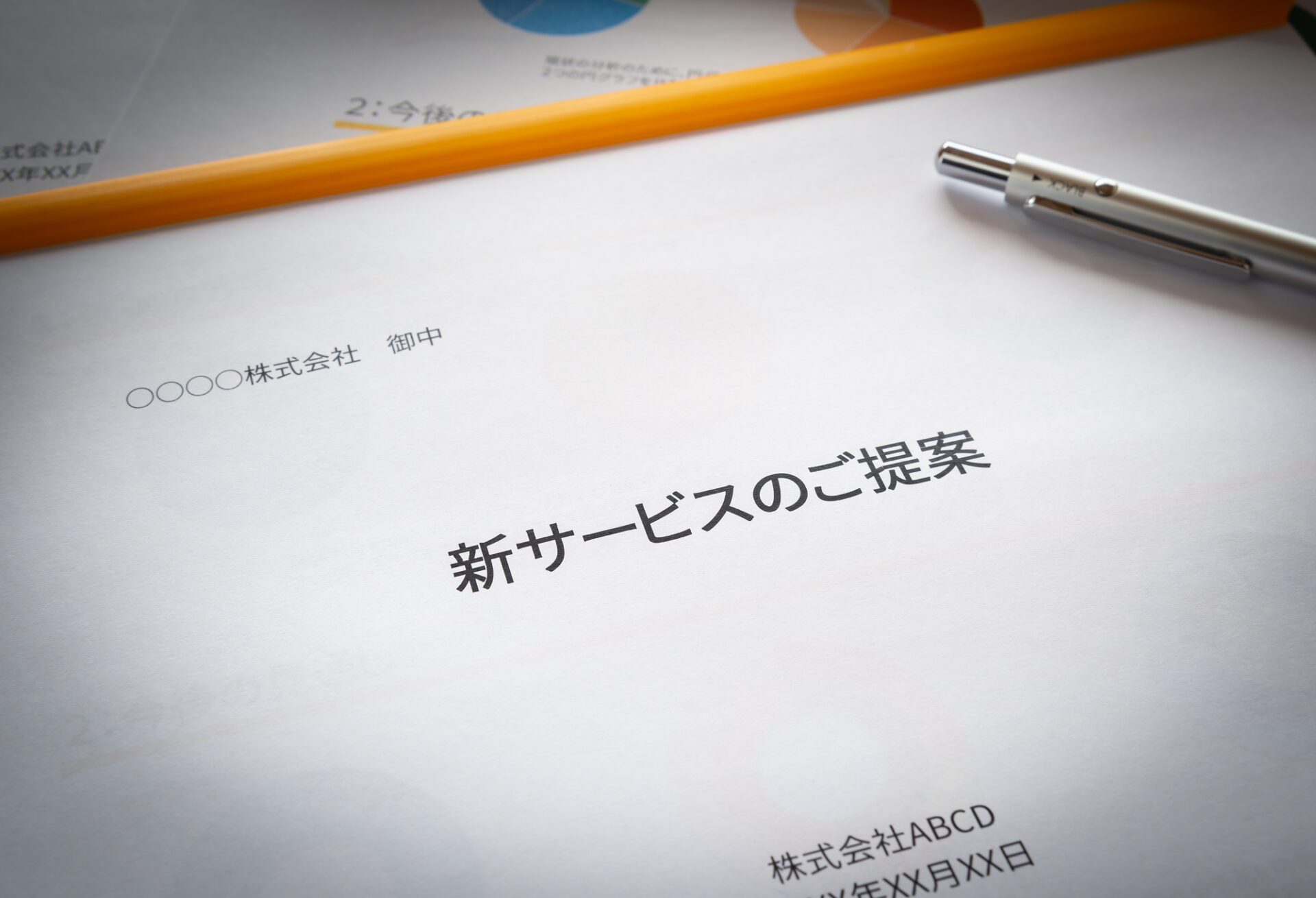企画書を書く際、どのように書いていますか。
書くべき項目を見出しにしたテンプレートを用いて、項目を埋めていくだけの方もいるかもしれません。
ですが、企画書を書く際に意識したいのは、ストーリー性を持たせることです。
どのようにすればストーリー性が出るのか見ていきましょう。

ただ項目を埋めるだけはNG
企画書のテンプレートを自分なりに用意している人や部署で雛型が用意されているといった職場もあるかもしれません。
書き漏れがないようにと、企画の目的、課題、現状分析、具体的施策、成果などと項目が並んでいるような、シンプルなテンプレートが多いと思います。
企画を通すためには、説得力を持たせるために必要となる項目について、具体的に示していくことが大切です。
ですが、ただ各項目を埋めていくと、それぞれが分断されてしまい、前後のつながりや関連性が不明確になることがあるので注意が必要です。
自分では1つの企画に向けて各項目を書いているつもりが、1つの流れができていないので、読み手や聞き手にはわかりにくくなります。
企画書を書く際に流れを意識して書かず、自分が書ける項目から埋めているような人は特に注意しましょう。
たとえば、目的や課題を書かずに、具体的施策のところだけを埋め、後から目的や課題を考えるような場合、やりたい企画だけが思いついているだけで、肝心の目的や解決したい課題が後付けになります。
自分では考えついたと思っても、全体を見るとちぐはぐな印象を与えます。
人は違和感を抱くと受け入れにくくなるので、企画の採用率も低下する可能性があるため注意が必要です。
ストーリーで考える
企画を考える時はストーリーで考え、それを企画書にも反映させていくことがポイントです。
なぜその企画が生み出されたのかから始まり、その企画を行うとどうなるのか、順を追って理解できるような、ストーリー性を持たせましょう。
また、なぜその企画を行う必要があるのか、その背景や理由がわかるエピソードがまず紹介されると、企画の必要性が受け入れやすくなります。
そして、企画を実行するとどうなるのか、それがわかる成果やメリットなども示せると、全体がつながります。
企画を実行した後の未来までイメージできるので、実行可能性が高まり、企画の採用率も高めることが可能です。
ストーリーの流れ
たとえば、企業や消費者の問題を解決するための企画を立てたい時には、次のようにストーリーを展開していきます。
「こんなお悩みはありませんか。」、「××が起こると大変ですね。」といった問題提起からスタートです。
次に、なぜ、その問題やお悩みが生じるのかを伝えます。
「実はその問題が起こるのは、こういう理由があったのです。」、「実は××は、〇〇が原因でした。」などとして関心を惹きつけ、問題やお悩みに関する現状分析を展開しましょう。
せっかく、関心を惹きつけたのですから、その関心を引き離さないよう、現状分析の結果を視覚的にも訴えかけます。
アンケート調査の結果や各種調査のデータをグラフや表、イラストなども用いて示します。
データや視覚化されたグラフなどで、原因や理由、背景などがわかると、これはなんとかしなくてはと思えてきませんか。
ストーリー的には、これはなんとかしなくてはと不安を持たせたり、これはどうにかしたいねと興味を掻き立てたりするのがポイントです。
そこで、どうすれば問題やお悩みを解決できるのか、企画を紹介します。
企画書だからと、最初に企画を出して、後から考えた背景などを紹介する方法もありますが、まずは、「こんな課題があります。」→「それはこんな事情から発生しました。」→「そこで、それを解決するために〇〇という企画を提案します。」といった流れのほうが話が入りやすいです。
企画実行後のストーリーまで
企画を行った際にどんなことが起こるのか、どんな成果がもたらされるのかまでストーリーが展開されないと、実行可能性が生まれません。
「この企画をすると問題が解決できます。」ではなく、具体的にどう解決され、どんな成果や相乗効果が生まれるのかも書いていきましょう。
ビフォーアフターをイラストで示したり、企画を行う時と行わない時の比較表を掲載したり、企画を実行した際のイメージを膨らませやすくすることが大切です。
まとめ
企画書を書く際には流れにストーリー性を持たせることを意識しましょう。
ストーリーとして展開していくことで、読み手や聞き手が引きこまれ、企画の必要性を感じる場合や企画に取り組みたいと思いやすくなります。
ストーリー性を持たせると、初めて見聞きする企画でもイメージが持ちやすくなり、実行可能性も高まります。