相手に伝わる企画書や提案書は、目次やページの構成がわかりやすいのが特徴です。
あまり企画書や提案書を書いたことがないと、どのように目次やページ構成を考えたら良いのかわからないのではないでしょうか。
企画書と提案書に分けて、目次やページ構成の作り方を紹介していきます。
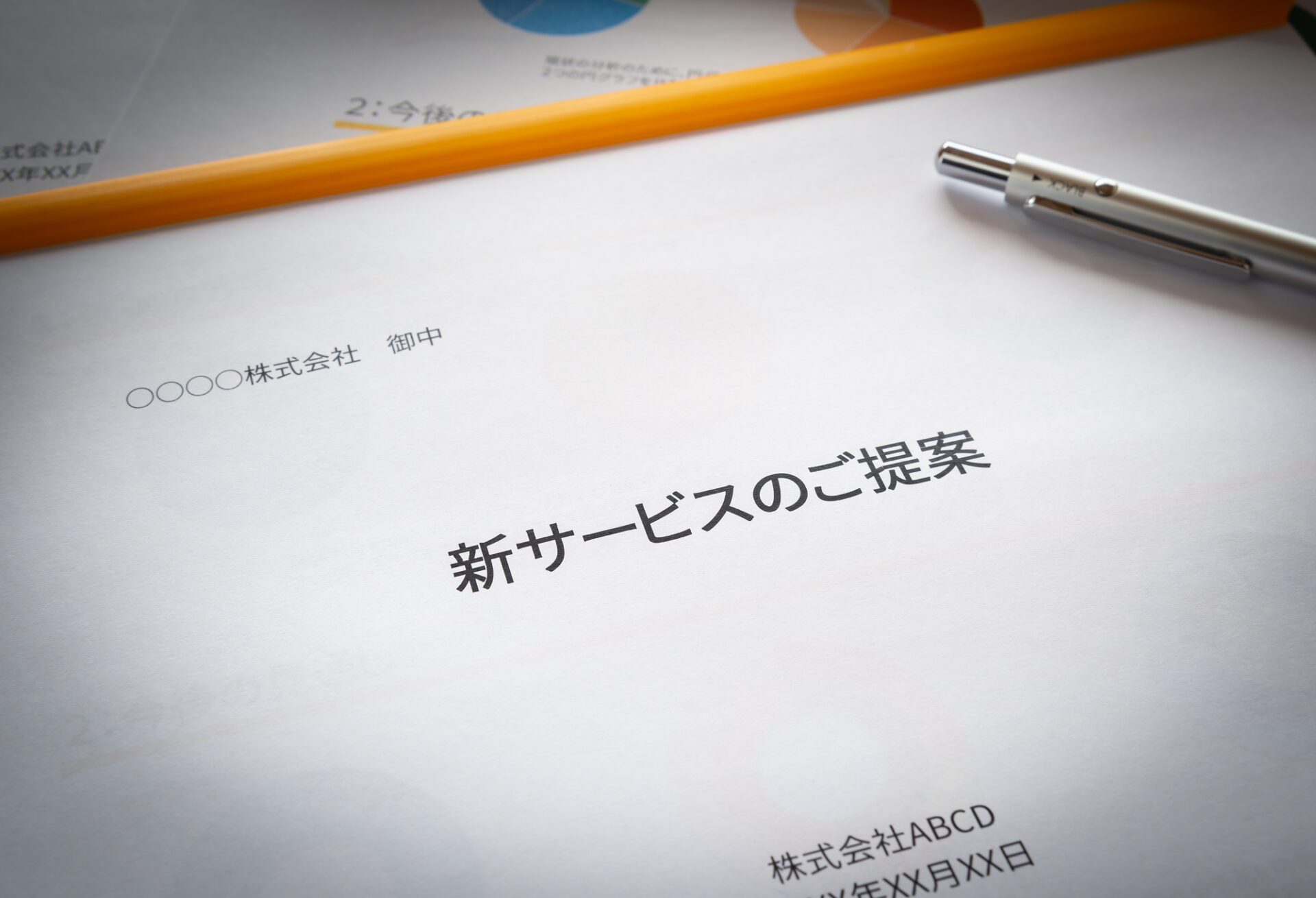
企画書の目次
特に企画書は実務レベルで相手に伝えなければいけないため、ページ数もある程度の枚数になってしまうでしょう。
話が伝わりやすいようにするためには、まず目次を付けましょう。
プロジェクトなどで相手がどんな企画かを見てくれる際、目次があればだいたいの話の内容がどう進行していくのか予想しやすくなります。
企画書はWordやPowerPointを使って作成する場合が多いと思いますが、どちらも目次は必ず作成します。
企画書のページ構成
企画書では、スムーズに読み進めてもらうためにもページ構成が重要です。
順番に違和感があると、相手も何を伝えたかったのかわからなくなってしまい、企画を通すか悩んでしまいます。
ここからは、企画書のページ構成を順番に説明していきます。
タイトルから決める
見る側は企画の内容がどんなものかわからないため、簡潔に内容を知りたいと思っています。
タイトルでは、今から何の企画内容の話が始まるのか、短く簡潔に書きましょう。
その後どんな話が始まるのか、目次を作ります。
なぜ企画しようと思ったのか目的と理由
企画をするにあたり、客観的な情勢の背景なども取り入れながら何で企画をしようと思ったのか理由も伝えます。
目的と理由がなければ、企画の内容だけ聞いても相手には伝わりません。
具体的に提案する
競合の商品などと客観的に比べながら、具体的に企画する内容を伝えていきます。
ここでも順番を考えながら説明をすると、企画についての具体的な内容も伝わりやすいので、覚えておくと良いでしょう。
想定されている課題があれば、解決策とセットで伝えると説得力もアップします。
市場調査や分析をし、結果と対応策を伝える
自分の思い込みでは企画書は通りませんので、市場調査や分析で客観的な部分をしっかりと見ていきます。
どのような対象者に調査をして結果がどうだったのか、年齢や性別、地域特性なども詳しく伝えましょう。
分析を行い、その結果からどんな方法を使えば対策としてピッタリだと感じたのかなども詳しく伝えます。
目標やスケジュール
どういった目標を持っているのかも一緒に伝えることも重要です。
この時曖昧に目標を伝えるのではなく、できる限り数値化して頭の中でパっとイメージしやすいようにすると良いでしょう。
スケジュールも淡々と伝えるよりも、フローチャートや時系列でわかりやすくまとめて相手がイメージできるようにします。
○月に何をするなど、具体的に伝えましょう。
最後に添付する資料があれば一緒に付けます。
提案書でも目次は重要
企画書と同じように相手に読んでもらうものだからこそ、わかりやすくなければなりません。
提案書でも目次を作成するのは重要で、これがなければ何の話が進むのかわかりにくくなります。
提案書でのページの構成
ここからは提案書の場合のページの構成を伝えていきます。
流れはほぼ企画書と同じで問題ありません。
テーマを伝える
まずは企画書と同じで、どのようなことを伝えたいのか相手がわかるように簡潔に伝えます。
提案内容をわかりやすく伝えると、後からの具体的な話が頭の中にも入ってきやすくなります。
具体的な提案内容や経緯
なぜ提案をしようと思ったのか経緯や具体的な内容を伝えていきます。
提案書のメイン部分でもありますので、相手に伝わりやすく文章の構成を考えながら書きましょう。
提案で得られる利益や効果
存続するためには、会社にとって利益や効果が重要です。
どの程度利益や効果があるのか、数値などでわかりやすく伝えましょう。
実現可能で無理のない提案だと思ってもらえると、受け入れてもらいやすくなります。
提案をする理由
そもそもなぜ提案をしようと思ったのかについても理由を伝えましょう。
納得させられる理由があり、さらに具体的な話もしっかりしているとなれば通りやすくなります。
スケジュールを伝える
本当に提案したものが実現するものかをイメージするためには、スケジュールの見通しも必要です。
具体的にどう進めていくのか、工程表も伝えます。
結語と添付資料を載せる
最後話が終わる段階に来たら、まとめとなる文章で締めましょう。
もし一緒に見て欲しい資料があれば、添付資料として載せます。
まとめ
どちらも目次を付けページの構成を意識すると話がわかりやすくなります。
文章にして企画書や提案書をまとめる時には、コンパクトに話すことも意識しましょう。
自分の考えをしっかりと伝えたいと思うあまり、長々としたものになってしまうかもしれません。
しかし、長いと相手側はよくわからなくなってきてしまいますし、逆に理解しにくくなってしまいます。
数値やグラフ、図なども使いながら、頭の中でイメージしやすいように伝えることも重要です。
実現性が高いと感じられると、企画書や提案書も採用されやすくなります。





