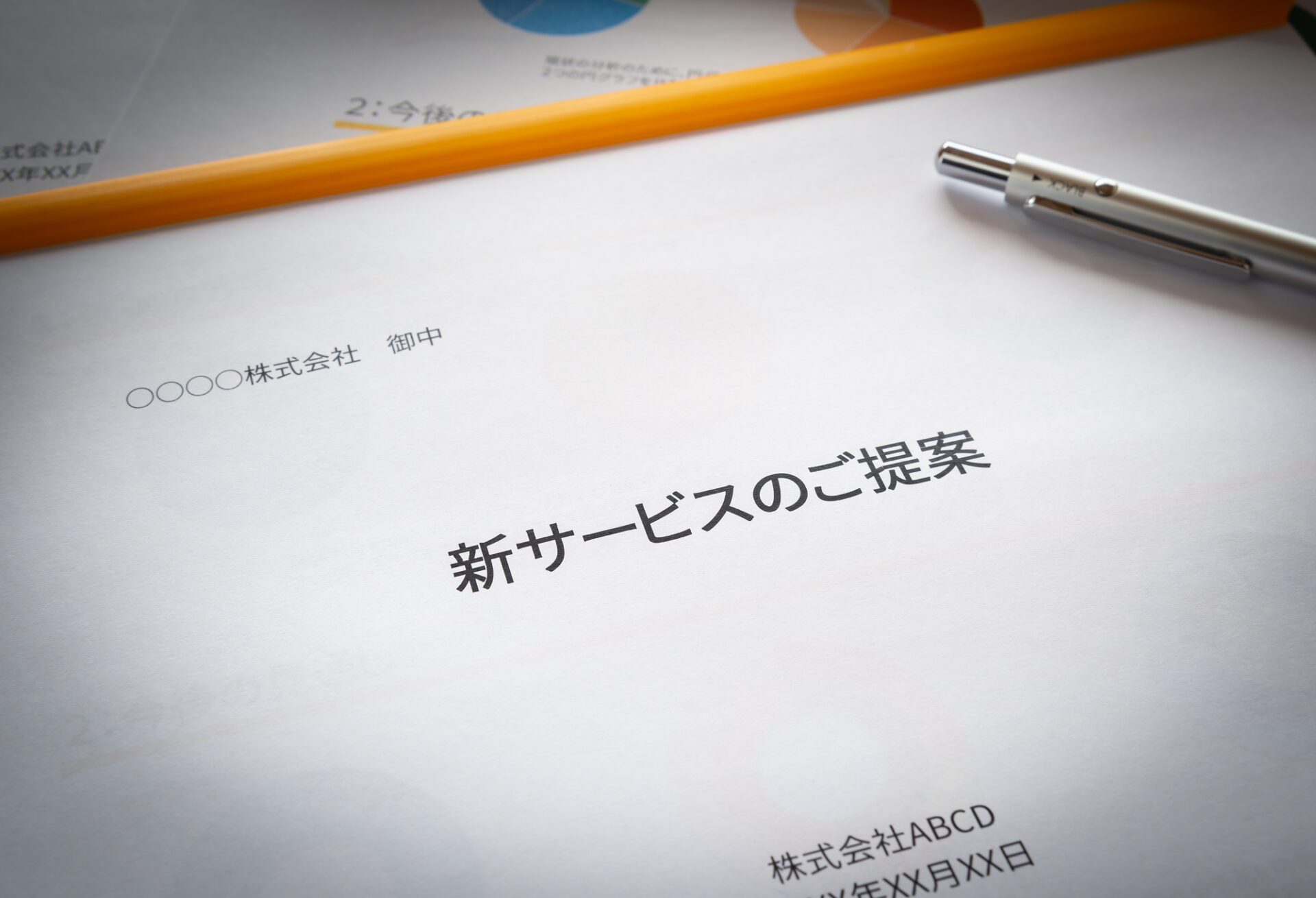社会人になると、自分の意見や考えを他者に伝えるシチュエーションが多くなります。
たとえば、商談やプレゼンテーションなどビジネスの場が挙げられるでしょう。
そういった場面において重要になってくるのが、「相手へ的確に情報を伝える能力」です。
人生を大きく左右しかねない場面において、相手に伝わらない話し方・文章の書き方をしてしまっては、せっかくのチャンスも逃してしまうでしょう。
そういったミスをおかさないためにも、「自分の主張が相手に伝わりやすい構成」を知り、それを活用していくことが求められます。
今回は、自分の意見や考えを他者に伝える際に使える構成を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

王道のPREP法
PREP法は、ビジネス文書やプレゼンテーションなどの場で大いに活用できる文章構成として有名です。
文章構成としてPREP法は非常にオーソドックスであり、実際に多くの現場にて使われています。
どのような構成を組んで自分の意見や考えを伝えれば良いか悩んでしまった場合は、まずPREP法を試してみるようにしましょう。
PREP法では、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論)、の順に文章を展開していきます。
最初にPoint(結論)を相手に伝え、その理由や具体的な例などを挙げた後、最後に再度Pointを説明するのが特徴です。
PREP法は相手が聞いてわかりやすい
特にビジネスの場において重要なのが、主張を相手に認識してもらうことです。
仮に具体的な例から話を始めた場合、その話の結論が見えてこなく、聞いている側としては何を伝えたいのかわかりません。
しかし、PREP法では主張つまり結論を真っ先に提示するため、聞き手はこの話の主題をしっかり把握できます。
とはいえ、結論が簡潔すぎても理解に至らないので、ある程度要点は押さえて述べるように注意しましょう。
前提となる結論を最初に話した後に、なぜそういった結論に至ったかの説明に進んでいきます。
そこで挙げられる理由や具体的な例も、結論を把握したうえで聞くことになるため、説得力が増します。
結論とそれに対応する理由・具体例を説明し、相手を十分に惹きつけたうえで、最後に改めて結論を述べてください。
最初だけでなく最後にも結論を語ることで話が強調され、印象に強く残るようになります。
PREP法はメリットが多い
PREP法はさまざまな場面にて活用できるため非常に便利です。
Point、Reason、Example、Point、の順番を守って文章を展開していけば、自分の意見を的確に相手へ伝えられるでしょう。
また、PREP法のメリットは情報伝達のスピードにもあります。
最初に結論を提示しているため話の要点が伝わりやすく、相手にとっても話をすぐ理解しやすいです。
そのほかにも、文章作成のスピードが上がる、構成を簡単に考えられるようになる、といったメリットが挙げられます。
このように、PREP法を導入するメリットは数多くありますので、ぜひ活用してみてください。
ほかにもある構成の事例
PREP法は非常に使いやすい文章構成ですが、伝えたい内容によってはうまく当てはめられないこともあります。
その場合はPREP法以外の構成も試してみましょう。
SDS法
PREP法がPoint、Reason、Example、Pointの略であったのに対し、SDS法はSummary(要点)、Details(詳細)、Summary(要点)の略語です。
この構成では最初と最後に要点を述べ、その間で詳しい説明を行います。
PREP法同様に重要な点を二度述べるため相手に要点が伝わりやすいです。
そのため、SDS法はニュース番組で多く用いられています。
短時間で印象付けたい場合にはSDS法を活用すると良いでしょう。
頭括型
頭括型では、まず意見を述べ、その後に実例を挙げます。
PREP法との共通点は最初に話の要点を伝えているところです。
結論と意見の違いはありますが、どちらも要点を最初に述べており、それによって一番伝えたいことの記憶が強く残るように工夫しています。
文章を作る際も、まず意見を書き、そこから実例を出すようにしましょう。
実例から考え始めてしまうと、自分が言いたかったことを忘れてしまいかねません。
具体例を挙げた後に意見を述べる「尾括型」という構成も存在しますが、話の要点を強く伝えたいのであれば頭括型を選んだほうが良いです。
四段構成(尾括型)
四段構成は「起承転結」と呼ばれることもある文章構成です。
名前の通り、構成が四段階に分かれており、4コマ漫画の構成に使われることもあります。
四段構成ではまず話のきっかけを述べ、それを発展させ、さらに場面や状況を変え、最後に結論を提示します。
緩急の起伏に富み、またじっくりと相手の関心を引き出していくのに便利なので、小説に用いられることも少なくありません。
しかし、結論が一番最後に来てしまうので、意見をすぐに伝えたい時にはあまり適していません。
たとえば、商談相手の関心を引き出したいときには四段構成が使えますが、簡潔に主張を伝えたい場面であれば頭括型を選ぶようにしましょう。
DESC法
米国の心理学者であるゴードン・バウアー氏が提唱したDESC法もご紹介します。
この構成は、相手との信頼関係を構築しつつ意見を伝達していくことに長けており、たとえば折衷案を要しなければならない場面で有効です。
PREP法やSDS法と同様にこの構成も略語で、Describe(描写)、Explain(描写)、Specify(提案)、Choose(選択)、の頭文字を取っています。
まず相手が置かれている状況を客観的に説明し、そのうえで自分の気持ちを述べていきます。
そして、相手にも理があるような解決策や折衷案を提示し、最後にどの行動を取るかを相手に選んでもらうのが、DESC法の流れです。
相手との協力関係を構築しやすいため、1対1のコミュニケーションでは効果を発揮しますが、複数人を相手にしてのプレゼンテーションなどには適していません。
まとめ
自分の意見や考えを相手に伝える場合には、その内容だけでなく、どのように語っていくかの構成にも気を配る必要があります。
PREP法をはじめとした文章構成をテンプレートとして活用し、それに伝えたいことを上手に当てはめつつ述べていけば、相手にしっかりと伝えられるようになるでしょう。
特にビジネスシーンではPREP法が有効です。
また、要点を強く印象付けたい場合にはSDS法が適しています。
このように、文章構成にはさまざまなパターンがありますので、シチュエーションや伝えたい内容に応じて的確なものを選んでみてください。